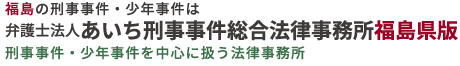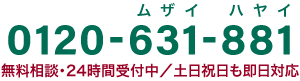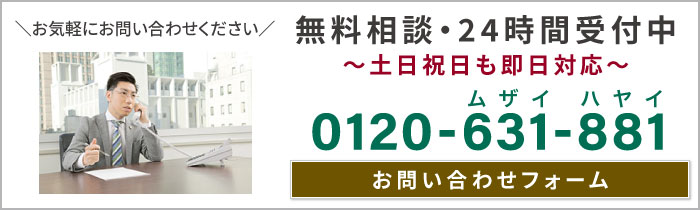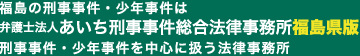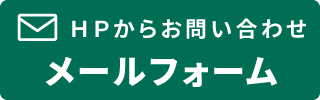覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
福島県会津若松市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
ある日、Aさんは警察から職務質問を受けました。
薬物のことで止められたわけではありませんでしたが、職務質問中に警察官がAさんの様子がおかしいと思い、尿検査を求めました。
Aさんは尿検査に応じ、その結果、Aさんが覚醒剤を使用していたことが分かりました。
そのままAさんは覚醒剤取締法違反の容疑で、会津若松警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反
覚醒剤は一時的に高揚感が得られますが、幻覚が現れたり睡眠障害の危険がある依存性の高い薬物で、覚醒剤取締法によって規制されています。
覚醒剤取締法第19条が覚醒剤の使用の禁止に関するもので、「次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
「次に掲げる場合」とは、「覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合」、「覚醒剤研究者が研究のため使用する場合」、「覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合」「法令に基づいてする行為につき使用する場合」の5種類です。
この条文における「使用」は、服用するだけを意味しておらず、薬品を製造するために使うことも覚醒剤を使用したことになります。
覚醒剤の使う対象も、自分に対して使う場合に限定されません。
他人に使用することも含まれており、他人に依頼して自身に使用させることも禁止されています。
人への使用はもちろんですが、家畜などに対して使っても覚醒剤取締法違反になります。
Aさんはインターネットで覚醒剤を購入して使用していました。
Aさんは覚醒剤の製造業者でも研究者でもなく、医師から交付を受けたわけでも法令に基づいて使用したわけでもありません。
そのためAさんの覚醒剤の使用には、覚醒剤取締法違反が成立します。
覚醒剤取締法第19条に違反した場合の刑罰は、「10年以下の拘禁刑」になります(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
執行猶予
覚醒剤使用の刑罰には罰金刑がないため、有罪になれば実刑になってしまいます。
しかし執行猶予を取り付ければ刑務所への服役を回避することができます。
執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
しかし執行猶予獲得の条件に「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡し」が含まれているため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反だとその条件を満たせない可能性があります。
そのため覚醒剤の使用で刑事事件になってしまった場合、速やかに弁護士に相談し、拘禁刑は3年以下になるよう弁護活動を行うことが重要です。
また、薬物による事件は逮捕の可能性が高くなりますが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
覚醒剤取締法違反になってしまった際は、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
覚醒剤取締法に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間365日対応しております。
覚醒剤の使用で刑事事件化してしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ、お気軽にご相談ください。