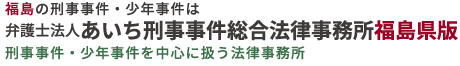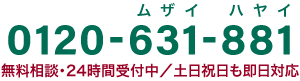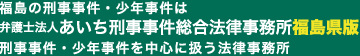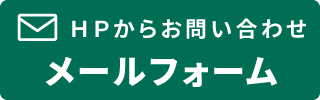Archive for the ‘交通犯罪’ Category
福島県須賀川市で高齢者によるひき逃げで逮捕
福島県須賀川市で高齢者によるひき逃げで逮捕
高齢者の方が自動車を運転中、前方不注意やブレーキの踏み間違え等によって人を負傷させてしまい、怖くなって事故現場から逃げ出したりするケース(ひき逃げ)とその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<刑事事件例>
福島県須賀川市の年金受給者Aさん(81歳)は、自動車でドライブに出かけ、その帰りに運転疲れでぼーっとしていたところ、交差点から飛び出してくる自転車に気付くのに遅れ、自転車に乗っていたVさんと衝突してしまいました。
Aさんは怖くなって事故現場から逃げ出してしまい(ひき逃げ)、事故を目撃した他の車の運転手が救急車と110番通報を行いました。
ひき逃げの被害者であるVさんは、福島県内の病院に緊急搬送され、意識不明の重体です。
その後、福島県警須賀川警察署は目撃者の自動車に備えていたドライブレコーダーを解析し、Aさんの身元を割り出し、Aさんを自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷罪)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いない。怖くなって逃げてしまった」と事実を認めています。
(フィクションです。)
上記刑事事件例は、令和元年8月26日、三重県警が、愛知県小牧市の82歳の無職男性を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の疑いで逮捕した事案をモデルにしています。
警察によると、被疑者は24日午後6時45分頃、三重県伊賀市の県道で軽乗用車を運転中、自転車に乗っていた同市の無職男性(80歳)をはね、そのまま逃走(ひき逃げ)した疑いがあり、被疑者男性は頭などを強く打って意識不明の重体とのことです。
被疑者は行楽の帰りだったといい、事故時に近くを通った車のドライブレコーダーから身元の特定につながったとのことで、被疑事実について「間違いない」と認めている模様です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪、ひき逃げ(あて逃げ)、酒気帯び運転など、2つ以上の法令違反を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
犯罪の成立という観点では、これらの罪はそれぞれ独立して成立しますが、刑事手続上の評価においては、2つ以上の罪は併合罪として扱われ、最も重い法定刑である過失運転致死傷罪を中心に、その法定刑に加重される形で量刑が決まっていきます。
例えば、通常の過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が基本ですが、これに無免許運転が加わった場合、10年以下の懲役と刑が加重されることになります(自動車運転処罰法第6条第4項)。
また、無免許運転以外の一般的な道路交通法違反との併合罪となった場合、成立する最も重い有期懲役刑にその2分の1を加えたもの(1.5倍)を長期とするため、15年以下の懲役が科される可能性が出てきます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
福島県須賀川市で、高齢者によるひき逃げの交通犯罪に係る刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
ひき逃げで殺人罪
ひき逃げで殺人罪
わざとひき逃げをして被害者を死亡させたという事件がありました。
「刑務所に入りたくて、わざとはねた」2人ひき逃げの男を殺人容疑で立件へ
(Yahoo!ニュース・読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~普通のひき逃げ事件かと思われたが…~
この事件は元々、福島県三春町の国道で、地域の清掃活動中の男女2人をトラックではねて死亡させた男が、無免許過失運転致死罪などの疑いで逮捕されたというものです。
まずはこの無免許過失運転致死罪という犯罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
自動車の運転を誤って人にケガをさせたり、死亡させた場合には、5条の過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となってしまうおそれがあります。
その時さらに無免許運転だった場合には6条4項により罰が重くなり、10年以下の懲役となる可能性があります。
このように事故を起こしたこと自体による罰則の他にも、その後、被害者を助けずに逃げてしまった場合には別途、道路交通法に定められた救護義務違反(10年以下の懲役または100万円以下の罰金)などに問われる可能性があります。
~今回は殺人罪が問題に~
ここまでで解説した犯罪は、間違って事故を起こしてしまった場合に成立しうる犯罪です。
しかし今回の男は取調べに対し、「刑務所に入りたくてわざとはねた」といった供述をしているようです。
間違ってではなく、わざと自動車ではねたとなれば、シンプルに殺人罪が成立する可能性があります。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
最高で死刑もありうるわけですので、誤って事故を起こした場合とは雲泥の差となります。
~逮捕後の手続きの流れ~
逮捕後の手続の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。
刑事手続の流れと弁護活動
逮捕後23日間の身柄拘束がされ、その後に刑事裁判がスタートします。
裁判中も保釈請求が通らない限り、身柄拘束は続きます。
裁判で実刑判決となれば刑務所に行くことになります。
一般的に弁護士は、まずは早期釈放を目指し、その後出来るだけ軽い処分・判決を目指して活動致します。
殺人罪などを含め、重い犯罪ではなかなか難しいところではありますが、必要以上に重い処分・判決となってご本人やご家族の負担とならないよう、サポートしてまいります。
~ぜひ弁護士にご相談を~
殺人罪が問題となる場合はもちろんですが、もっと軽い事件・事故の場合を含めて、あなたやご家族が逮捕されたり取調べを受けたという場合には、どんな犯罪が成立し、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安な点が多いと思います。
事件の内容をお聴き取りし、今後の見通しをご説明致しますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。
福島県田村市で無免許・無車検運転
福島県田村市で無免許・無車検運転
自動車等の運転にあたって法律で義務付けられている運転免許や車検を行わないことによって生じる法的責任とその刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県田村市で自営業を営むAさんは、ある日交通事故に巻き込まれてしまい、福島県警田村警察署の警察官による現場検証の際に運転免許証の提示を求められたところ、自分の運転免許証の有効期限が超過しているにも関わらず運転していたこと(無免許運転)、および、自動車検査証(車検)の有効期間も超過していたことが発覚し、道路交通法違反(無免許運転)および道路運送車両法違反の疑いで、警察に任意の事情聴取を求められました。
Aさんは、自分がどのような刑事責任を負うことになるのか不安になり、警察で事情聴取を受ける前に刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※フィクションです)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日々様々な交通犯罪に関する法律相談を承っており、特に、自動車運転上の過失により人を負傷させてしまったケース等による過失運転致傷罪の刑事事件が最も多い印象を受けます。
上記刑事事件例のように無免許運転や無車検運転、あるいは自賠責に加入していない等の法令違反の刑事事件は、法律相談の数としては珍しいですが、特に自営業で毎日自動車に乗る方等がしばしば法律相談にいらっしゃることがあり、今回のブログで取り上げたいと思います。
無免許運転については、大まかに3分類があり、1つ目が全く免許を持っていない場合(免許を持っていない車種を運転する場合も含みます)、2つ目が取得していた免許の有効期限が切れていた場合、3つ目が免許停止や免許取消の処分を受けたにも関わらず運転していた場合となります。
以上すべての場合について、道路交通法によれば、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
次に、道路運送車両法は、自動車は、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならないとしており、これに対する罰則として、6月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
さらに、自動車検査の有効期間と自賠責保険の有効期間は同一であることが多く、無車検運転をしている場合は自賠責に入っていないかその有効期限が切れている可能性が高く、自賠責保険に未加入のまま自動車運転を行った場合、自動車損害賠償保障法違反のため、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
このような交通犯罪事案では、道路交通の安全に対する罪として処罰されるため、被疑者の反省や再犯防止の姿勢を示す等の情状主張を行うことが重要となるため、早い段階で刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧め致します。
福島県田村市で無免許運転や無車検運転が発覚して刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
福島県郡山市であおり運転で刑事事件化
福島県郡山市であおり運転で刑事事件化
他の自動車に対して急停止したり幅寄せをする等の悪質な走行妨害運転、いわゆる「あおり運転」で刑事事件化するケースと、その刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件例】
福島県の地方公務員Aさんは、福島県郡山市の国道において、自分を追い越した前の車に対して、過剰なクラクションや幅寄せを行ったとして、福島県警郡山警察署によって、暴行罪および道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは逮捕事実の一部について否認をしています。
(実際の逮捕事実を元に、場所や事実の一部を変更したフィクションです。)
【今注目のあおり運転の交通犯罪の刑事責任】
上記刑事事件例は、平成30年12月、兵庫県三木市の山陽道で、1.4キロにわたってあおり運転を繰り返したとして、兵庫県警が同月10日、陸上自衛隊所属の男性被疑者を暴行罪および道路交通法違反の容疑で逮捕した事案をモデルにしています。
警察の発表では、被疑者は、前を走る女性が運転する車の前に割り込んで進路を妨害し、道路上に停止させるなどした疑いがありますが、逮捕事実の一部を否認しているようです。
あおり運転に対しては、年々罰則の厳罰化が進んでおり、警察庁も通達を出しているように、あおり運転に対して、「あらゆる法令の適用」をもって厳重に処罰するとの姿勢を強めています。
神奈川県の東名高速におけるあおり運転での死亡事故が大変注目を集めたことは記憶に新しく、危険運転致死傷罪で起訴された被告人に対して、平成30年12月10日、検察官は懲役23年を求刑し、第一審判決は懲役18年とされました(現在控訴審が進行中)。
上記事案はあおり運転による死亡事故の中でも大変悪質な態様で、かつ2名の死者が出ていることから、検察官が重い処罰を求めたと考えられますが、一般的に危険運転致死傷罪の量刑について言えば、自動車保険による損害の補填や示談成立等により4、5年の執行猶予付き判決を獲得している事例もある反面、犯行態様が悪質なものについては、上記事案のように殺人罪に等しいとの価値判断から、10年を超える懲役刑が科された事件も見られます。
また、仮に事故を起こして人を死傷させるという結果が起きなかったとしても、適切な車間距離を保持しないことは、道路交通法第26条違反であり3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性もあります。
※ただし車間距離不保持違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金の支払いで罰則を免れることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの交通犯罪事件を取り扱っております。
福島県郡山市で、あおり運転による交通犯罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご利用ください。
福島県伊達市でひき逃げで逮捕
福島県伊達市でひき逃げで逮捕
自動車で人身事故を起こしてしまったにも関わらず、怖くなった等の事情で事故を報告しないまま立ち去ってしまった「ひき逃げ」の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事件例>
福島県伊達市の道路を車で走行していた会社員Aさんは、急に飛び出してきた小学生Vを轢いてしまったものの、事故を起こしてしまったパニックでひき逃げをしてしまいました。
Vは市内の病院に搬送されたものの、いまだ意識不明の重体です。
事故現場付近の目撃情報から、福島県警伊達警察署はひき逃げの可能性が高いと判断し、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いで、ひき逃げ犯人の車と思われる自動車の追跡を続けています。
(フィクションです)
上記刑事事件例は、令和元年9月26日午後4時ごろ、大阪府堺市の市道で、横断歩道を渡っていた同区の小学3年(9歳)の男児が車にはねられ、足の骨を折るなどの重傷を負った件で、車が事故現場から逃走していることから、大阪府警堺警察署がひき逃げ事件として車の行方を追っている事案をモデルにしています。
警察によると、現場は片側1車線の信号機がある交差点で、逃げた車は黒色の軽乗用車との目撃情報があり、警察が付近の防犯カメラを回収するなどして捜査を進めています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる交通犯罪の刑事事件のご相談では、過失運転致死傷罪および道路交通法違反(ひき逃げ、あて逃げ)などの交通犯罪を行ってしまったとご相談される方多くいっらっしゃいます。
ひき逃げや当て逃げについては、事故を起こしてしまった場合には速やかに警察や救急へ連絡しましょうと警察庁などが啓蒙活動を続けていますが、人身事故を起こしてしまったことに対して強い恐怖と後悔を覚え、事故発覚が怖くなって逃亡してしまう(ひき逃げ)事案は依然として多く見受けられます。
弊所に寄せられたひき逃げ事案では、一度は逃げてしまったものの、警察に自ら出頭したり、時には弁護士も同行して出頭するなどして、人身事故を起こしてしまったことを捜査機関に認め、被疑者の身元や身元引受人などをしっかりと説明した上で、警察からの捜査に協力することをきちんと主張していくことで、捜査段階では逮捕を免れ、在宅のまま捜査が続けられるケースが多く存在します。
一般論として、ひき逃げを起こしてしまった場合に捜査機関から逮捕される場合の要因としては、被疑者が捜査機関に対して出頭をしないこと、つまり逃亡を続けていることや、被害者の被害が重大であること、事故現場の見分から判断して、例えば猛スピードによる衝突など、自動車運転上の過失が非常に大きいと判断される場合などでは、捜査機関は犯行の悪質性や今後の捜査に対する悪影響を考慮して被疑者の身柄確保(逮捕)に踏み切る可能性が高いと思われます。
交通犯罪に関する刑事事件は、被疑事実に対する認めまたは否認、被害の程度等によって、逮捕リスクが大きく変わる傾向がありますが、特に被害の甚大なひき逃げ事件では、一度被疑者が事故現場から逃走しているという事実も鑑み、逮捕リスクは比較的高くなる傾向もあるため、刑事事件化した場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
福島県伊達市でひき逃げで刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料相談や初回接見サービスをご検討ください。
ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首する前に弁護士に相談
ひき逃げで自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~ケース~
福島県伊達市に住むAさんは、自家用車を運転し買い物に出かけました。
その帰り道で、信号機のない交差点に進入したところ、左方向から進入してきた自転車とぶつかってしまいました。
ぶつかったショックで気が動転したAさんは、そのまま現場から走り去ってしまいました。
自宅に戻ったAさんは、やはり警察に連絡すべきだと考え直しまし、伊達警察署に出向こうとしています。
Aさんは、自分の行為は自首に当たるのか、当たるとしたらどのような効果があるのか、と疑問に思っています。
(フィクションです。)
自首が成立する場合とは
多くの方が、自ら警察署に出頭することを「自首」であると思われていますが、ただ単に警察署に出頭するだけでは、法律上の自首は成立しません。
自首が成立するには、満たさなければならない要件があります。
自首の要件
自首とは、犯罪が捜査機関に発覚する前に、犯人が自分の犯罪事実を捜査機関に申告し、その処分を求めることをいいます。
自首については、刑法第42条に次のように規定されています。
刑法第42条
1.罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2.告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
自首が成立する要件は、次の4つです。
(1)犯罪事実が捜査機関に発覚する前
自首が成立するには、犯罪事実が捜査機関に発覚する前に、犯罪の申告をする必要があります。
犯罪事実が捜査機関に発覚する前というのは、捜査機関が全く犯罪について把握していない場合だけでなく、犯罪事実は把握しているが、犯人が特定されていない場合も含まれます。
ただ、単に犯人の所在が不明な場合には、発覚前とは言えません。
(2)捜査機関
ここでいう捜査機関とは、検察官または司法警察職員です。
(3)自発性
犯罪の申告は、犯人が自発的に行わなけば、自首は成立しません。
例えば、取り調べや職務質問に対して、犯罪事実を自白した場合は自首とはなりません。
(4)処罰を求める意思
自己の犯罪事実の申告には、自己の訴追を含む処罰を求める趣旨が明示的または黙示的に含まれていなければなりません。
犯罪の一部を隠すためや、自己の責任を否定するために申告が行われる場合には、自首には該当しません。
上のケースで考えてみると、Aさんが事故後現場から逃亡していますが、事故の相手方が警察に通報していれば、犯罪事実は捜査機関に発覚していると言えるでしょう。
しかし、犯人がAさんであると特定する前に、警察署などに出頭し犯罪事実を申告するのであれば、自首が成立する可能性はあります。
さて、自首が成立した場合には、どのような効果があるのでしょうか。
自首の効果
(1)刑の減軽
自首について規定している刑法第42条には、自首をした場合には、刑を減軽することができると書かれています。
これは、自首が成立した場合に、裁判所が必ず刑を減軽することを定めているわけではなく、あくまでも「できる」のであり、刑が減軽されるのは裁判所の裁量によります。
減軽の方法についても、刑法で定められています。
・死刑を減軽する場合は、無期の懲役もしくは禁固、または10年以上の懲役もしくは禁固とする。
・無期の懲役または禁錮を減軽する場合は、7年以上の懲役もしくは禁固とする。
・有期の懲役または禁錮を減軽する場合は、その長期および短期を2分の1を減ずる。
・罰金を減軽する場合は、その多額および寡額の2分の1を減ずる。
・拘留を減軽する場合は、その長期の2分の1を減ずる。
・科料を減軽する場合は、その多額の2分の1を減ずる。
(2)情状
刑の減軽となる可能性の他に、自首した事実が被疑者・被告人に有利な事情として考慮されることがあります。
自首したという事実は、被疑者・被告人の反省を裏付けるものとして、被疑者・被告人にとって有利な事情となるからです。
(3)身体拘束の回避
自首したこと、もしくは、自首が成立せず「自ら出頭した」場合であっても、その事実により、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと判断され、逮捕や勾留が回避できる可能性を高めることになります。
ひき逃げ事件の場合、現場から一度逃亡していますので、逮捕される可能性は通常の交通事件と比べて高くなっています。
しかし、その後、犯人が自首または出頭してきたことで、逮捕されずに在宅事件として捜査が行われるケースも少なくありません。
以上が、自首が成立した場合の一般的なメリットとなります。
犯罪を犯してしまい、自首をご検討されているのであれば、早期に弁護士にご相談ください。
そもそも自首が成立するのか、自首をした場合のその後の流れや見込まれる処分など、自首をする前に知っておいたほうが、少しでも不安を和らげることになるでしょう。
自首後の弁護も予め弁護士に依頼しておくのも、事件を穏便に解決する一つの手段です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
自動運転システム故障で過失運転致死傷罪?
運転支援システムの故障により事故が起きた場合、過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
Aさんは福島県二本松市内の高速道路を走行中、前の車に追突してしまい、1人を死亡させ、もう1人にケガをさせてしまいました。
Aさんの運転していた車には、車間距離等を計測して一定の間隔を保ちながら走行できる運転支援システム(クルーズコントロール)が搭載されていました。
しかし事故当時このシステムが故障しており、Aさんも寝ぼけながら運転していたため本件の事故が起こってしまいました。
Aさんはどのような罪に問われるのでしょうか。
(このケースはフィクションです。)
~過失運転致死傷罪が成立するか~
近年、AI技術の向上に伴い自動車運転の自動化が急速に進んでいます。
各メーカーの見立てによれば、2025年頃には完全な自動運転機能を搭載した自動車の一般での実用化の可能性も高いとのことです。
このような自動化は、運転能力の不十分な者、たとえば免許返納を考えるような高齢者や、四肢に障がいのある方などにも自動車による移動を可能にするものであり、ますますの発展が望まれるところです。
しかし同時に、運転の自動化は法律的に難しい問題をいくつも抱えています。
本件のような、運転補助システムが正常に働かず結果として事故が起きてしまった場合に、事故の刑事責任を運転者に問うべきかが議論の的となっています。
通常、居眠りなどで交通事故を起こして相手に死亡や負傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立します。
「過失」とは簡単に言えば不注意です。
不注意で事故を起こし、他人を死傷させると、最大で7年の懲役が科される可能性があります(自動車運転処罰法5条)。
(*スピード違反や飲酒等危険な運転による場合はさらに重い罪が科されます)
では、本件でAさんは過失運転致死傷罪は成立するのでしょうか。
本事例では、Aさんの車のクルーズコントロールシステムが正常に作動しませんでした。
しかし、正常に作動することを前提に運転していたのですから、寝ぼけながら運転していたとしても、刑事責任を負わなくてもいいのではないかとも思えます。
しかし、最近似たような事例において、事故直前の被告は前方注視が困難なほど強い眠気に襲われており、そのような場合には運転を中止する義務があったとした裁判例が存在します(横浜地裁令和2年3月31日判決)。
同判決は「中止義務に違反した被告の過失は相当に重い」とすら述べています。
とすれば本ケースでも、Aさんに過失運転致死傷罪が成立する可能性があるということです。
なお、この判決は、被告の車が停止等しなかったことは「システムの故障か機能の限界かは判然としない」という事実認定を前提にしています。
つまり、システムの故障が原因であっても、そもそもの性能の限界が原因であっても、上手くシステムが作動せずに事故が起きた場合には、運転者が責任を問われる可能性があるということになります。
システムを過信せずに運転する必要があるということになります。
ただしこの判決は、あくまでもこの事故の事情を前提とした判断です。
つまり、当時の道路や車の走行状況、掲載されていたシステムの性能、運転者の不注意の程度、その他すべての事故当時の具体的状況を前提に、過失ありという判断がなされているということです。
当然、居眠りなどしていなければ責任を問われない可能性もあります。
また今後、自動運転システムの性能自体も向上を続け、いずれは運転席に人がいないような自動運転車も実現されるでしょう。
完全自動運転の自動車では、搭乗者に刑事責任は問えない、という結論になる可能性も否定できません。
~弁護士にご相談ください~
私たちの事務所には、交通事故を含む刑事事件を専門にする弁護士のみが在籍しています。
運転サポートシステムの関わる事故はもちろんですが、それだけでなく、刑事事件に関してお困りのことがあれば、初回は無料で相談に乗っていますので、ぜひご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でした。
人身事故の弁護活動
~ケース~
愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を負っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~過失運転致傷罪~
交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文で構成されており,自動車や無免許運転の定義,事故の類型や法定刑を定めています。
Aさんの起こしてしまった過失運転致傷罪は第5条で以下の様に定められています。
(過失運転致死傷)
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。
今回のケースでAさんはその場で警察と救急車を呼んでいますので過失運転致傷罪のみが成立すると考えられます。
なお,交通事故を起こしてしまった場合に警察や救急車をその場で呼ばなかった場合,道路交通法の救護義務などに違反することになります。
これらはいわゆる「ひき逃げ」と呼ばれるもので,逮捕・勾留のリスクも増加してしまいます。
また,悪質であるとみなされ,刑事裁判となってしまう可能性も高くなります。
Vさんの怪我は全治1カ月ですので傷害が軽いとはいえません。
そのため,但し書きにある刑の免除規定を適用することはできないでしょう。
~弁護活動~
人身事故に限らず,交通事故を起こしてしまった場合の弁護活動として第一に身柄拘束の回避が挙げられます。
逮捕・勾留といった身柄拘束がされるかは捜査機関の判断によりますが,事故直後に自発的に警察などに通報していれば逃亡のおそれなどがないと判断され,逮捕・勾留といった身柄拘束がされない可能性が高くなります。
一方で,警察等に通報せずにその場から去ってしまう,「ひき逃げ」をしてしまうと逃亡したことになってしまいので,逮捕・勾留されるリスクは高くなります。
身柄拘束の回避として,検察官に勾留しないように意見書を出したり,勾留されてしまった場合に裁判所に勾留に対する準抗告を申し立てることが考えられます。
ただし,交通事故で勾留が認められた場合,準抗告が認容されない可能性が高くなっています。
交通事故では被害者の方と示談を成立させ,「加害者を許す」という宥恕があるかどうかが最終的な結果に大きく影響します。
過失運転致傷罪では示談を成立させ宥恕があるという場合には実刑判決となる可能性が低くなります。
示談をし宥恕があれば怪我の程度によっては起訴されず,起訴猶予となる場合もあります。
今回のケースでは全治1ヵ月の骨折という決して軽くない怪我をしてしまっていますので,起訴猶予とならない可能性もあります。
しかし,示談をし宥恕があれば罰金刑となる可能性も高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
人身事故を起こしてしまったというケースで示談を成立させ,宥恕を頂き,起訴猶予の不起訴となった事例も多く手掛けて参りました。
人身事故を起こしてしまった方は一人で悩まずにまずは0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談や,警察署などでの初回接見のご予約を24時間年中無休で受け付けています。
自転車事故で重過失傷害罪
福島県福島市に住む高校1年生のAさんは、近くのスーパーへ行こうと自転車を運転していました。
その際、ズボンのポケットに入れていたスマートフォンからLINEの通知音が鳴ったため、AさんはLINEを確認しようとスマートフォンを見ました。
すると、返信を入力していた際に突然「危ない」という声が聞こえ、正面に高齢の男性Vさんが立っていることに気づきました。
慌ててブレーキを掛けたAさんでしたが、不幸にもVさんと接触してしまい、Vさんに骨折などの怪我を負わせてしまいました。
この件で福島北警察署が現場に駆けつけ、Aさんは重過失傷害罪の疑いで福島北警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで、Aさんの両親は示談について弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【重過失傷害罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
重過失傷害罪は、刑法211条の後段にあるとおり、「重大な過失」によって人に怪我を負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「重大な過失」とは、簡単に言うと不注意の程度が著しいことを指すと考えられています。
甚だしい不注意により結果が生じてさえいれば、生じた結果の軽重は問わない点に注意が必要です。
上記事例では、Aさんがスマートフォンを見ていたことでVさんに気づくのが遅れ、ブレーキが間に合わず接触して怪我を負わせています。
一般に、自転車の運転中に周囲に気を配るのは当然であり、それを怠った時点で落ち度があるという非難は避けられないかと思います。
加えて、Aさんにとって運転中にスマートフォンを見る必要性はなかったはずであり、更にLINEの返信となると意識が他にいかなくなることは容易に想定できます。
これらの事情からすれば、Aさんには「重大な過失」があったと認定されても不思議ではありません。
そうすると、これが原因でVさんに怪我をさせている以上、Aさんに重過失傷害罪が成立する可能性はあるでしょう。
【少年事件における示談】
刑事事件における示談とは、謝罪や被害弁償などにより当事者間で一応事件が解決したことを示す合意です。
主に被害者の納得という側面を捉えて、検察官や裁判官は示談の締結を理由に処分を軽くすることがよくあります。
そのため、一般的に示談は重要であり、事件によっては不起訴や執行猶予になる可能性が飛躍的に高まります。
ただ、少年事件、すなわち未成年者が起こした刑事事件については、必ずしも示談をすれば丸く収まるというわけではない点に注意が必要です。
少年事件において最終的に目指すところは、心身が未成熟である少年に適切な措置を施し、更生を促すなどして健全な育成を実現することです。
この点から、成人が起こした通常の刑事事件と比べて、少年本人の反省や将来性がより重視されるようになっています。
このような観点から示談を考察した場合、その効力は通常の刑事事件ほど大きくはないと言えます。
なぜなら、示談は形式的には謝罪を含みますが、結局のところ重視されているのは被害者が受けた損害の補填だからです。
示談の締結と少年の反省とは、論理必然的につながるようなものではありません。
特に、未成年者が与えた損害は保護者が補填するのが通常なので、場合によっては未成年者に一切の損失はないということになります。
そのため、示談から少年の反省の程度などを汲み取ることができず、結果的に効果が限定的なものと評価されやすいというわけです。
以上の点を含め、少年事件において最良の結果を目指すためには、事件の内容や少年の人柄などに応じた多種多様な活動を行うことが大切となります。
ですので、少年事件については弁護士に相談するのが得策でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、示談を含めて少年ひとりひとりに合わせた最適な付添人活動を行います。
お子さんが重過失傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
飲酒運転で略式罰金
福島県福島市に住むAさんは、学生時代の友人と飲み会をすることになり、車で市内の居酒屋へ行きました。
その日は翌日が休日だったため、車で寝てから翌朝帰宅しようと考えていました。
飲み会が終わった頃には午前2時を過ぎており、Aさんは予定どおり車内で5時間程度の睡眠をとりました。
そして、朝になって帰宅しようと運転した際、左折する際に誤って物損事故を起こしてしまいました。
Aさんの通報で現場に駆けつけた警察官は、Aさんから酒の匂いがすることに気づいて呼気検査を行いました。
そうしたところ、数値が0.2を示したことから、Aさんは飲酒運転の疑いで福島警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、最終的な処分が略式罰金となる可能性が高いと説明しました。
(フィクションです。)
【飲酒運転について】
一般的に、飲酒運転はその名のとおり酒を飲んで運転する行為を指すかと思います。
飲酒運転は道路交通法が定める罪の一つですが、この罪には2種類があることはご存知でしょうか。
その2種類とは、①酒気帯び運転と②酒酔い運転と言われるものです。
以下では、それぞれについて概要を説明します。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転は、飲酒した運転手の様子に関係なく、身体に一定程度以上のアルコールを保有した状態で運転した場合に成立します。
具体的なアルコールの基準値は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムです。
実務においては呼気検査の方が多い傾向にあるので、基準値のうち重要なのは0.15ミリグラムの方と言えます。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
②酒酔い運転
酒酔い運転は、「アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態」で運転した場合に成立します。
酒気帯び運転のように基準値が定められているわけではありませんが、検知の結果も考慮要素の一つに当たると考えられます。
それに加えて、飲酒運転の疑いがある運転手に対し、警察官が挙動を観察するなどして判断するものと思われます。
たとえば、質問に正しく答えられているか、歩行の際に千鳥足になっていないか、といった点が見られることになるでしょう。
罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
【略式罰金について】
飲酒運転の罰則は、数ある道路交通法違反の中でも重い部類に属します。
そのため、複数回行えば裁判に至る可能性が飛躍的に高まります。
一方、初犯の場合については、いわゆる略式罰金というかたちで裁判を行うことなく終了することも多いのが実情です。
以下では、略式罰金の意味や、略式罰金を受け入れることによるメリットとデメリットについて説明します。
なお、多くの交通違反に課される反則金の制度(いわゆる青切符)は、以下の略式罰金と異なるため注意が必要です。
略式罰金とは、略式手続という特殊な裁判手続により下される罰金刑のことです。
通常の裁判との最大の違いは、裁判所の法廷ではなく書面上で審理が行われる点です。
略式罰金制度の主眼は、軽微かつ簡素な事件を迅速に処理し、被告人や関係機関の負担の軽減を図るというものです。
そのため、わざわざ法廷で裁判を行ったりせず、公衆の目に触れない書面の上だけで有罪・無罪の判断と刑罰の決定を速やかに行うことになるのです。
上記のような特徴を持つ略式罰金は、被告人にとって裁判に伴う肉体的・精神的負担が軽いというメリットがあると言えます。
ただ、迅速な処理の意識は、ともすれ慎重な判断を欠くことにつながりかねません。
そこで、略式罰金とする場合は被疑者の同意が必要となること、一定期間内であれば正式裁判を要求できること、の2点が定められています。
特に、きちんと争うことで無罪になる可能性が高いのであれば、敢えて略式罰金を受け入れないというのも一つの手でしょう。
自身の事案について疑問を抱かれたら、ぜひ弁護士にその旨ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき略式罰金に関するご相談をお受けします。
飲酒運転を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)