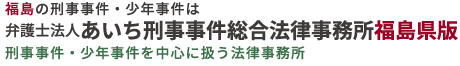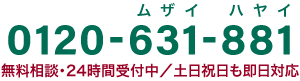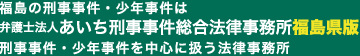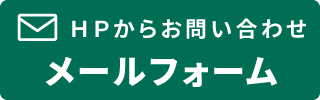Archive for the ‘刑事事件’ Category
住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕
住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕
【事例】
福島県伊達市在住の男性Aは、過去のトラブルから恨みを抱いたB女に対し、わいせつ行為をしようとその帰宅を狙いB女宅に押し入り、顔面への殴打、ガムテープの顔面への貼付、両手首を縛り上げる等の暴行を行い、反抗ができない状態にした上でわいせつ行為をしました。
この際、B女はケガもしてしまいました。
その後、AはBをそのままにして立ち去る際に財布が落ちていたのを発見しこれを持ち去りました。
一週間後、B女が被害届を提出し、Aは警察官によって住居侵入罪、強制わいせつ致傷罪、強盗罪で逮捕されました。
(このストーリーはフィクションです)
~住居侵入罪~
今回のストーリーでは、
①住居侵入罪(刑法130条前段)
②強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項、176条)
③強盗罪(236条1項)
が成立する可能性がありますので、順番に解説していきます。
まずは、住居侵入罪から。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aの行為は、赤く色付けした部分に該当します。
つまり、Aはわいせつ行為をする目的だったので「正当な理由がない」状態で、B女宅という「人の住居」に、B女の意思に反して立ち入っているので「侵入」しているといえます。
したがって住居侵入罪が成立するでしょう。
~強制わいせつ致傷罪~
続いて、強制わいせつ致傷罪について見ていきましょう。
刑法176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法181条1項
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
AはB女に対し、顔面への殴打等の「暴行…を用いてわいせつな行為をした」ので、強制わいせつ罪が成立します。
その際、B女がケガをしてしまったので、強制わいせつ致傷罪が成立することになります。
刑罰も無期懲役または3年以上の有期懲役(上限は20年)です。
被害者死亡の場合を含めた規定ではありますが、ケガをさせた場合は、させない場合よりもぐっと重く処罰される可能性があるわけです。
~強盗罪~
最後に、強盗罪について見ていきましょう。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
今回のAは、財布を奪う目的で暴行をしたわけではありません。
しかし、わいせつ目的で行った暴行により、すでにB女が反抗できない状態になっています。
この状態を利用する形で財布を持ち去っているので、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」であることに違いはなく、強盗罪が成立すると判断される可能性は十分考えられます。
~逮捕後の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。
~弁護士にご相談ください~
また、出来るだけ判決を軽くするためには、被害者の方に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要です。
しかし、性犯罪の被害者の方々にとって、加害者本人はもちろん、その家族と示談の話をするのは心理的負担が大きく、応じてくれない可能性が高いです。
しかし弁護士を挟むことにより、示談に応じてくれる可能性を上げることができますし、適切な内容・金額での示談締結の可能性も上げることができます。
さらに、ご本人は厳しい取調べにどう対応したらよいかわからないと思います。
弁護士は逮捕中の被疑者と面会(接見)する権利を有しており、取調べや裁判に向けたアドバイスできますし、家族の方からの伝言を伝えることなどもできます。
ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件と少年事件の専門家である弁護士が多く在籍しているため、迅速かつ適切な対応が可能となっています。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。
落書き・ビラ貼りによる建造物損壊罪で逮捕
落書き・ビラ貼りによる建造物損壊罪で逮捕
公衆トイレに落書きやビラ貼りをして、建造物損壊罪の容疑逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
福島県福島市に住むAさんは,日ごろのいらだちから,同市内の公園の公衆トイレに,スプレー缶で「税金泥棒」「福島市長は辞任しろ」等と落書きし,また,役所に反感を示すような内容のビラを30枚ほど貼り付けました。
監視カメラの映像からAさんの犯行と特定され,Aさんは福島県福島警察署の警察官により,建造物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
~建造物損壊罪とは~
公衆トイレに落書きやビラ貼りをしたAさん。
建造物損壊罪という犯罪が成立する可能性があります。
刑法260条
「他人の建造物……を損壊した者は,5年以下の懲役に処する」
あまり聞きなじみのない犯罪かもしれませんが、簡単に言えば,他人所有の建物を壊した場合に成立する罪です。
一般にもよく知られる器物損壊罪は,「前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し……者は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」(261条)となっています。
建造物損壊罪の方が懲役の上限が長く、罰金で済む可能性もないため、より重い犯罪ということになります。
損壊の対象が物よりも一般的には価値が高い建造物であることや、中にいる人に危険が及ぶ可能性があるといった理由により,器物損壊罪よりも重い刑罰が定められています。
~壊してないけど~
今回、Aさんは公衆トイレを物理的に壊したわけではありませんが,それでも建造物損壊罪は成立するのでしょうか。
ここでは、条文に出てきた「損壊」という言葉の意味が問題となります。
建造物損壊罪における「損壊」には、建造物を物理的に破壊した場合の他に,建物の効用を害する一切の行為が含まれると解釈されています。
つまり、物理的に壊れていなくても、建造物としての利用が困難になれば、建造物としての効用が害されているわけなので「損壊」に当たり、建造物損壊罪が成立することになるわけです。
今回のような公衆トイレの場合には、落書きやビラ貼りがなされても、トイレとして利用することができるので、効用を害していないといえる気もします。
しかし,公衆トイレに大きな落書きがなされた事件で最高裁判所は,落書きが「損壊」にあたると判断しています(最決平成18年1月17日刑集60巻1号29項)。
この判例は,わかりやすく言うと,
・外観・美観に工夫が凝らされ誰でも利用しやすい状態だった公衆トイレが,大きな落書きによって汚い・治安が悪そうといった印象を与えるなど,利用することに抵抗感ないし不快感を与えるような状態となっている
・しかもすぐに消せる落書きではなく,原状回復にはある程度費用がかかるなど相当な困難が伴う落書きだった
といった事情により、きれいで誰でも利用しやすい公衆トイレとしての効用を害しているので,「損壊」に当たると判断したものといえるでしょう。
この判例は,トイレへの落書きが常に「損壊」に当たると言っているわけではありません。
しかしこの判例によれば,今回のAさんの事例においても,公衆トイレが元々どのような外観であったか、落書きやビラの大きさ・ビラの枚数・その内容がどうだったか,簡単に消したり剥がしたりできるかといった事情によっては,自由に使える公衆トイレとしての効用を害しているとして建造物損壊罪が成立する可能性があるということになります。
~弁護士にご相談ください~
このように法律の世界では,一般的な使われ方とは微妙に異なる意味で言葉が使われたり,その言葉に該当するかどうかの判断のために多くの事情を考慮しなければならないなど、難しい面があります。
それゆえ,一般の方が犯罪にならないと思っていたことが犯罪だった,ということもあります。
そしてご自身やご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり取調べを受けた場合には,刑事手続がどのように進んでいくのか,いつ釈放されるのか,どれくらいの刑罰を受けるのか,示談はどうやって行えばよいのかなど,不安だらけだと思います。
事件解決に向けてサポートしてまいりますので,まずは一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご利用を、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での無料法律相談のご利用をお待ちしております。
強制わいせつ罪で示談
強制わいせつ罪で示談
強制わいせつ罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは,午後8時頃に福島県伊達市内を歩いていたところ,うっすらと制服姿の女性Vさんの姿が目に入りました。
Aさんらが歩いていたところは人気が少なく,なおかつ街頭もあまりない薄暗い場所でした。
そこで,Aさんはわいせつな行為をしようとVさんに近づき,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言いました。
そのうえで,Vさんのスカートの下から手を入れ,Vさんの陰部に指を挿入しました。
数秒して,Aさんはふと我に返って大変なことをしたと思い,「すみません」と言ってその場を離れました。
後日,被害届を受けた伊達警察署が捜査を開始し,Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,示談を行うべくVさんの両親と連絡を取ることにしました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は,暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合に成立する可能性のある罪です。
ただし,被害者が13歳未満の者であれば,わいせつな行為のみをもって強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪における暴行・脅迫は,相手方の犯行を困難にする程度のものを指すと考えられています。
つまり,暴行・脅迫が簡単に抵抗できるような弱いものであれば,わいせつな行為があったとしても強制わいせつ罪は成立しない可能性があるということです。
とはいえ,実際の裁判においては,暴行・脅迫が強制わいせつ罪に値するほど強度のものだったと比較的容易に認定される傾向があります。
このあたりの認定については,「そこまで強い暴行・脅迫じゃなかったから大丈夫だろう」と安易に考えるべきではないと言えるでしょう。
次に,「わいせつな行為」の意義については,裁判例において「いたずらに性欲を刺激・興奮させ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,もって善良な性的道義観念に反する行為」を意味すると判断されています。
陰部に指を入れる行為は,一般的に「わいせつな行為」に当たるとされる可能性が高いです。
上記事例では,AさんがVさんに対し,背後から口を押えて「静かにしないと殺す」と言ったうえで,陰部に指を入れるというわいせつな行為に及んでいます。
そうすると,Aさんに強制わいせつ罪が成立する可能性は高いでしょう。
【示談の難しさ】
上記事例のような強制わいせつ事件で自ら示談をしようとするのは,率直に言って相当の困難がつきまといます。
まず,通り魔のようなかたちで見ず知らずの者に強制わいせつ罪を犯した場合,逮捕の可能性が相当な高さになることが見込まれます。
もし逮捕されてしまうと,示談締結に向けた被害者との接触は当然ながら不可能となってしまいます。
また,仮に逮捕されなかった,あるいは親族などに示談を任せる場合も,今度は被害者がどこの誰なのか知ることができないという問題が立ちはだかります。
一応捜査機関に「示談したい」という意向を伝えることは考えられますが,加害者本人やその親族などの頼みとなると,それに応じて連絡先を教えてくれるかどうかは分かりません。
そして,何らかの手段で被害者と示談交渉を行えたとしても,常に交渉の決裂や不十分な合意といったリスクはつきまといます。
最悪の場合,こちらとしては示談金を払って合意を取り交わしたつもりだったのに,そのことを効果的に証明する手立てが何もなく全てが水の泡となることもありえます。
以上のようなリスクは,弁護士であればその可能性を下げる,あるいは完全に遮断することが期待できます。
特に強制わいせつ事件の示談は何かとデリケートなので,やはり弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士は,どのような事件でも示談の締結に向けて全力を尽くします。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
傷害致死罪で情状弁護
傷害致死事件で情状弁護
傷害致死罪と情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福島県福島市に住むAさんは、以前から近所に住むVさんと折り合いが悪く、たびたびお互いに悪態をつくなどしていました。
ある日、AさんはVさんから「お前なんていつでも殺せるからな」と言われ、「それができるならやってみろよ。いくじなし」と挑発しました。
すると、Vさんが突如Aさんの首を絞めてきたため、焦ったAさんはVさんを蹴り飛ばしました。
そして、Vさんに馬乗りになったうえ、胸倉を掴んで道路に頭を叩きつけました。
その現場に福島警察署の警察官が居合わせ、Aさんを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
その後、搬送先の病院でVさんの死亡が確認されたことから、Aさんの嫌疑は傷害致死罪へと切り替えられました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は、情状弁護を行うべくすぐに準備に取り掛かりました。
(フィクションです。)
【傷害致死罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、他人に傷害を負わせ、その結果として他人が死亡した場合に成立する可能性のある罪です。
わざと行った行為により他人を死亡させる点では、殺人罪と共通する点があると言えます。
殺人罪との最大の違いは、端的に言って行為のときに殺意があったかどうかです。
もう少しかみ砕くと、殺人罪は「殺そうと思って殺した」というケースで成立するのに対し、傷害致死罪は「殺すつもりはなかったが結果的に死亡した」というケースで成立します。
ただし、取調べや裁判でこのような供述をしたからといって、そこから直ちに殺人罪か傷害致死罪かが決まるわけではありません。
人の内心は目に見えないものなので、被疑者・被告人の供述だけでなく客観的な事情も踏まえて判断が下されます。
たとえば、包丁で被害者の胸部を複数回刺したという場合、殺意があったと評価され、傷害致死罪ではなく殺人罪が成立すると考えられます。
【情状弁護という手段】
「情状弁護」という言葉を聞きなれない方は多くいらっしゃるかもしれません。
ですが、情状弁護は、法廷においてはごくありふれたものだと言うことができます。
その内容とは、罪を犯したこと自体は認めているケース(つまり自白事件)において、被告人に有利な事情を主張することで少しでも刑を軽くする、というものです。
日本の刑事事件は大半が自白事件なので、自然と法廷における弁護活動も情状弁護となることが多いと言えます。
それでは、上記事例で情状弁護を行ううえで、どのような事情が重要となるでしょうか。
第一に、AさんがVさんに対して暴行を働くに至った経緯が挙げられるかと思います。
今回のケースでは、Vさんによる暴行がAさんの挑発に起因すること、AさんがVさんに馬乗りになってまで暴行を加えています。
そうすると、正当防衛であり犯罪が成立しないと主張するのはおそらく難しいです。
ですが、それでも過剰防衛の範疇ではあったと主張して、刑の減軽を求めることが考えられます。
また、上記事例では明記されていませんが、犯行以外の事情も情状弁護を行ううえでやはり重要となります。
たとえば、Aさんに前科がないこと、事件後に真摯な反省が見られること、Vさんの家族に謝罪や賠償を行ったこと、などが考えられます。
以上のような主張は、単に法廷で陳述するだけではなく、陳述を認めてもらうに値する証拠もなければ十分な効果を発揮できません。
効果的な情状弁護を行うのであれば、やはり弁護士への依頼が不可欠と言っても過言ではないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、一つ一つの事案を丹念に検討して情状弁護の主張を組み立てます。
傷害致死罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
強要罪で勾留決定に対する準抗告
強要罪と勾留決定に対する準抗告について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、福島県会津若松市内のコンビニで弁当を買った際、従業員のVさんが割り箸をつけなかったことに怒りを覚えました。
そのことをVさんに指摘したところ、Vさんはしぶしぶ謝罪するような態度を見せたことから、Aさんは激怒して土下座を要求しました。
Vさんは、Aさんに「てめえいい加減にせんとしばくぞ」などと言われたことから、さすがにまずいと思い土下座をしました。
後日、Vさんが会津若松警察署に被害届を提出したことがきっかけとなり、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんは勾留されることになったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告を行うことにしました。
(フィクションです)
【強要罪について】
刑法第二百二十三条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
暴行や脅迫を手段として、他人に本来行う必要のない行為を無理やり行わせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
最近時々見られる土下座強要も、それに至る過程で脅迫や暴行が加えられていれば、強要罪が成立すると考えられます。
強要罪は、他人の自由な意思決定を妨げることを問題視する罪だとされています。
そのため、手段となる暴行や脅迫は、相手方を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないと考えられています。
また、たとえ暴行や脅迫がその程度に至っていたとしても、それと結果との間に因果関係が存在する必要があります。
ですので、たとえば被害者が憐れみの情を感じて行為に及んだ場合は、強要罪の成立が否定されることとなります。
【勾留決定に対する準抗告とは】
被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留決定に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることができます。
勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断が覆されることはそう多くありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが強要罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
放火罪で保釈
放火罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福島県の会社に勤めるAさんは、新入社員のVさんがちやほやされているのに嫉妬し、Vさんに嫌がらせをしてやりたいと考えました。
そこで、Aさんは従業員用のロッカーにあったVさんの服に火をつけ、ロッカーに入っていた物を燃やしました。
幸いにも従業員のひとりが早期に出火を発見したため、そう燃え広がらないうちに鎮火されました。
その後通報により警察が駆けつけ、Aさんは事情聴取ののち建造物等以外放火罪の疑いで北海道猪苗代警察署に逮捕されました。
Aさんはその後起訴されたため、弁護士に保釈を依頼しました。
(フィクションです。)
【建造物等以外放火罪について】
第百十条
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
物を燃やすことで成立する放火罪には、①現住(現在)建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つに分かれます。
そもそも、放火罪にいう「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、炭坑を指します。
そのため、建造物等放火罪は、この4つ以外の物を放火した場合に限って成立するということになります。
建造物等放火罪の成立を認めるには、建造物等以外を放火したことで「公共の危険」が生じたと言えなければなりません。
この「公共の危険」とは、不特定または多数人の生命・身体・財産に対する危険だと考えられています。
そのため、たとえば火の大きさや周辺に存在する物からして、対象物以外に被害を与える危険性が認められないケースでは、建造物等以外放火罪は成立しないと考えられます。
この場合には、対象物の効用を害したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Aさんがロッカーの中にあるVさんの服に火をつけ、Vさんの物を燃やしています。
そのため、Aさんは「放火」によって「焼損」を生じさせたと言えます。
加えて、犯行現場は他の従業員の物が入ったロッカーが並ぶロッカールームであり、人の出入りも当然にありえたと考えられます。
そうすると、「公共の危険」も発生していることから、Aさんは建造物等以外放火罪として1年以上10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
【保釈による身柄解放】
放火罪は重大な犯罪であるため、捜査機関に発覚すれば逮捕および勾留の可能性はかなり高いと言えます。
そして、もし勾留中に起訴されると、被疑者勾留が被告人勾留へと切り替わり、最低でも2か月は身体拘束が伸びてしまいます。
そうした事態に陥った際、身柄解放を実現する有力な手段として保釈の請求が考えられます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金額の金銭を預けることで、一時的に被告人を釈放する手続を指します。
保釈の最大の強みは、起訴前に釈放を実現できなかった事件においても、釈放を実現できる可能性がある点です。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などを図ると没収される担保のような役割を持ちます。
そして、その金額は不審な行動を抑制するに足る高額なものとなっているので、そうした行動には出ないだろうと考えられて釈放が認められやすいのです。
ただし、保釈を認めてもらうには、その前段階として保釈請求が認容される必要があります。
保釈請求に当たっては、法律の専門家である弁護士の視点が重要となることは否定できません。
ですので、保釈を目指すのであれば、保釈請求を含めて弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、長期間拘束されている方の保釈の実現に全力で取り組みます。
ご家族などが放火罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
建造物損壊罪で示談
建造物損壊罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
北海道紋別郡に住むAさんは、隣の住宅に住んでいるVさん宅からの騒音にうっぷんが溜まっていました。
ある日、Aさんは遂に騒音に耐え切れなくなり、Vさん宅のガラス戸に向かって拳大の石を投げつけました。
これによりガラス戸が割れたことから、VさんはAさんが犯人であることを突き止めたうえで北海道遠軽警察署に被害届を出しました。
焦ったAさんは、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、財物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえば塗料で建物を汚す行為なども建造物損壊罪となる余地があります。
また、建造物のうちどこまでを建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。
たとえば、建物の壁の損壊が建造物損壊罪に当たることは理解できるかと思いますが、壊さずとも付け外しができる網戸を損壊した場合はどうかといった具合です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。
器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意しておきましょう。
【示談の重要性】
建造物損壊罪は、人の建造物を損壊する点で個人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した場合については、被害者との示談の成立が非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。
示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、内容の差はあれ、示談の存在は被害者の許しを推認させる事情となり、それが国家による刑罰権の行使を控えさせる事情となるのです。
ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に臨まなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂や、実が伴わない形だけの示談の締結といった事態に陥りかねません。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に任せるのが得策です。
弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、自身のノウハウを駆使して的確な示談交渉を行います。
建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
詐欺罪と黙秘権
詐欺罪と黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
福島県郡山市に住むAさんは、知人のVさんに対して「値上がり確実の未公開株がある」という嘘の話を持ち掛けました。
Aさんの言葉巧みな誘いにより、VさんはAさんに対し、株の代金として50万円を交付しました。
このような手法により、Aさんは1000万円近くの利益を得ました。
しかし、被害者複数名が警察に相談したことで、Aさんは詐欺罪の疑いで郡山警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、黙秘権について説明しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、他人から財産を騙し取った場合に成立する可能性のある罪です。
具体的な行為の内容は、①欺罔行為(欺くこと)によって、②①による相手方を誤信させ、③財産を交付させる、というものです。
それに加えて、④自身の行為が詐欺罪に当たる行為であることを認識している必要があります。
上記事例では、AさんがVさんに対して値上がり確実な未公開株があるかのように偽り、その存在を信じたVさんから50万円を受け取っています。
この行為は、上記①②③の全てを満たし、なおかつ④の認識もあると考えられます。
そうすると、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります。
ちなみに、仮にVさんが嘘だと見破りつつ何らかの理由で金銭を交付した場合、詐欺罪は成立しないと考えられます。
なぜなら、①欺罔行為と③財産の交付はあるものの、②Vさんの誤信を欠いているからです。
ただし、欺罔行為の存在により詐欺未遂罪が成立する可能性はあります。
【黙秘権を行使すべきか】
逮捕されているか否かを問わず、被疑者・被告人には黙秘権の行使が認められています。
黙秘権とは、その名のとおり供述を拒否することができる権利です。
そのため、取調べや裁判などにおいても、聞かれたことに対して答えないという選択をすることができます。
ただ、黙秘権が権利として存在しているからといって、それを無闇に行使するのはおすすめできません。
まず、黙秘権のメリットとして、自己の供述が捜査に活用されるのを防ぐことができるという点が挙げられます。
この点は、取調べにおける誤導や虚偽の自白などを防げることから、実際には罪を犯していないという否認事件でも意味を持つと言えます。
ですが、黙秘権を行使すると、捜査機関や裁判所からの印象はほぼ確実に悪くなることが見込まれます。
捜査機関としては、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして逮捕に積極的になったり、取調べにおける圧力を強めたりすると考えられます。
一方、裁判所としては、有罪になった場合に反省が見られないとして量刑を重くすることが考えられます。
以上で見たように、黙秘権には諸刃の剣と言うべき側面があります。
ですので、黙秘権の行使が妥当かどうかについては、個々の事案に応じた慎重な判断が必要となるでしょう。
加えて、黙秘権の行使は二者択一であり、捜査の途中で黙秘権を行使する(あるいはその逆)ことは得策とは言えない場合があります。
ですので、黙秘権の行使を少しでもお考えなら、可能な限り早めに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて黙秘権を行使すべきか的確にお答えします。
詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
暴行罪で示談
暴行罪で示談
暴行罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、福島県二本松市の駅にて電車に乗ったところ、あとから駆け込み乗車をしてきたVさんにぶつかられました。
Aさんは文句を言いましたが、Vさんは不満げに「すいません」とだけ言い、反省の色が全く見られませんでした。
それに苛立ちを覚えたAさんは、Vさんの胸倉を掴んだうえで背後のドアに押しつけました。
その場に車掌が通りかかり、Aさんは降車させられて暴行罪の疑いで二本松警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで、Aさんは弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、数ある犯罪の中で比較的なじみのある方ではないかと思います。
その存在をご存知の方も多いでしょう。
今回は、暴行罪について意外と知られていなさそうな事柄を中心に見ていきます。
まず、暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力や物理力を行使する一切の行為だと考えられています。
この定義から、「暴行」には殴る蹴るといった行為以外にも様々なものが含まれる可能性があることが分かります。
上記事例では、AさんがVさんに対し、胸倉を掴んだうえ背後のドアに身体を押しつけています。
こうした行為のうち、少なくともドアへの押しつけは「暴行」に当たるのではないかとお考えになる方は多くいらっしゃるでしょう。
ですが、それだけでなく胸倉を掴む行為についても、不法な有形力の行使として「暴行」に当たる可能性があるのです。
次に、暴行罪の条文を見てみると、「傷害するに至らなかったとき」も暴行罪の要件となっていることが読み取れます。
つまり、暴行によって傷害を負った場合については暴行罪が成立せず、傷害罪などのより重い罪が成立することになります。
場合によっては、事件の捜査が進んだことで暴行罪から傷害罪へと罪名が切り替わることもあるでしょう。
【暴行事件における示談】
正直なところ、暴行罪の罰則は数ある犯罪の中で比較的軽く、初犯であれば低額の罰金刑で済むことも珍しくありません。
ですが、たとえ刑罰の内容が低額の罰金だったとしても、前科として私生活に不利益が及びうることには変わりありません。
必ずというわけではありませんが、たとえば会社への就職、資格の取得、海外旅行などに影響する可能性があります。
上記のような不利益を回避するためには、不起訴を目指して被害者と示談を締結することが有効な手段となります。
示談は特定の事件に関する当事者間の合意であり、加害者が謝罪と被害弁償を行ったことや、被害者が厳しい処分を望んでいないことなどが示されます。
刑事事件においては、加害者を罰するべきか検討するに当たって、権利や利益が侵害された被害者の意思も尊重します。
そのため、被害者との示談の締結が明らかとなれば、検察官としても不起訴の判断を下しやすくなるのです。
ただ、示談という行為に対しては、「悪いことをしておいて金で解決する」という誤ったイメージをお持ちの方もいらっしゃいます。
そのため、示談交渉に当たっては、発する言葉一つ一つを慎重に選ぶなど細部に気を配ることが示談締結の鍵となります。
こうした交渉は弁護士の知識と経験が活きる場面なので、示談交渉は弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、どのような案件でも責任を持って示談交渉に取り組みます。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)
脅迫事件で逮捕され弁護士が接見
脅迫罪と弁護士の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
Aさんは、アイドルグループのメンバーであるVさん(福島県伊達市在住)の大ファンで、ブログやSNSのチェックからイベントの参加に至るまで応援に熱を注いでいました。
ある日、Aさんが何気なく週刊誌を見たところ、Vさんが交際相手と思しき人物と手をつないで歩く姿を撮影した写真が目に入りました。
それからほどなくして、Vさんのブログ上で「昨年より一般人の方と交際させていただいております」という発表がありました。
これに業を煮やしたAさんは、インターネット上の掲示板やSNSで「Vの家に行ってめった刺しにする」などと書き込みました。
このことを把握したVさんが被害届を出したことで、Aさんは脅迫罪の疑いで伊達警察署に脅迫罪の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【脅迫罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、その名のとおり人を「脅迫」した場合に成立する可能性のある罪です。
脅迫罪における「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を指すと考えられています。
上記事例では、AさんがVさんに対して「Vの家にめった刺しにする」という脅迫を加えています。
「めった刺し」という言葉は、通常刃物などで対象を複数回刺す意味で用いられるかと思います。
このような言葉自体が他人に恐怖心を抱かせるものですし、それが交際を発表したアイドルに向けられたとなると尚更です。
そうすると、AさんはVさんの生命または身体に害を加える旨を告知して脅迫したと言え、脅迫罪が成立すると考えられます。
脅迫という行為には、事案次第で脅迫罪より重い罪が成立する危険性があります。
たとえば、脅迫を用いて金銭を得れば強盗罪や恐喝罪に、相手方に義務のない行為を強いれば強要罪になる可能性が出てきます。
このように、脅迫により生じた結果いかんで明らかに刑罰が重くなるおそれがあることは留意すべきです。
【弁護士による迅速な接見の重要性】
刑事事件の被疑者に対して行われる身体拘束には、短期の身体拘束である逮捕と、長期の身体拘束である勾留の2段階があります。
逮捕後の流れを大まかに説明すると、逮捕から2~3日の間に勾留をすべきか検討され、勾留されると先述の期間に加えて10~20日の範囲で拘束が継続されます。
弁護士による接見には、一般の方が行う接見(面会)にはない様々なメリットがあります。
そのうちの一つとして、逮捕されてから勾留に至るまでの2~3日間でも接見を行えるという点が挙げられます。
日本全国の大半の警察署においては、勾留決定が下されるまで一般の方が面会を行うことが許されません。
つまり、一般の方が面会をする頃には、既に長期の身体拘束が決定して取調べなどの捜査が本格化しているのが通常と言えます。
これでは、逮捕された方がいつ釈放されるか分からないまま徐々に衰弱していき、取調べなどで対応を誤ってしまうという事態が生じかねません。
そうした事態を回避するために、弁護士による早期の接見が重要となるのです。
上記の接見を含めて、刑事事件は時間との闘いを強いられる場面が少なくありません。
裏を返せば、どの段階であっても弁護士の早期の介入がプラスになりうるということです。
ですので、事件がいずれの段階にあるか気にするよりも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、刑事事件のプロとしてお申込み後可能な限り早く接見に向かいます。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)