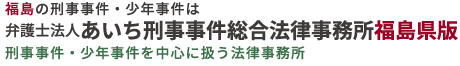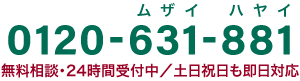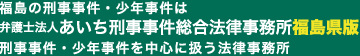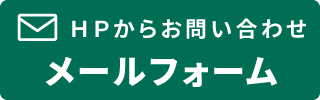Archive for the ‘少年事件’ Category
少年によるひったくり事件 福島市鎌田月ノ輪山
ひったくり事件を起こした場合に科される罪名について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
福島市のひったくり事件
アルバイトAくん(17歳・男子)は、福島市鎌田月ノ輪山の路上で、帰宅途中の無職Vさん(70代・女性)の持っていた鞄をひったくったとして、福島警察署によって、窃盗罪の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
【ひったくり事件】
窃盗罪は、少年が起こすことが多い犯罪の1つです。
窃盗罪にも、様々な類型がありますが、少年事件においては、万引き、自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
ひったくりとはバッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為をいいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【少年事件】
20歳未満の者が犯罪を起こした事件または犯罪を起こす可能性がある事件を少年事件といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、① 犯罪少年、② 特定少年(18歳・19歳の犯罪少年)、③ 触法少年、④ 虞犯 (ぐ犯)少年の4種類に分類されます。
① 犯罪少年(14歳以上18歳未満の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や、教育的なはたらきかけにより、少年審判を行う必要がないと判断された場合、少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、① 不処分、② 保護観察、③少年院送致、④ 児童自立支援施設等送致、⑤ 検察官送致、⑥ 児童相談所長送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年事件を扱う法律事務所の弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
少年が大麻で逮捕~少年院送致を回避には
非行歴がある少年が大麻で逮捕された件で、少年院送致を回避するためにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所静岡支部が解説します。
福島県郡山市に住む高校生のAさん(17歳)は、知人から勧められて大麻を吸引していたところ、郡山警察署の警察官から職務質問、所持品検査を受けてしまいました。Aさんは、ズボンの右ポケットの内に大麻入りのチャック付きポリ袋を入れていたため、警察官に大麻取締法違反(所持の罪)で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの両親はAさんが過去に傷害事件を起こし保護観察の保護処分を受けた非行歴を有していたことから、今度は少年院送致になるのではないかと心配になり、まずは弁護士にAさんとの接見を依頼して今後のことを相談することにしました。
(事実を基に作成したフィクションです。)
~大麻は薬物への入り口~
平成30年版犯罪白書によると、少年の覚せい剤取締法違反における検挙人員は平成10年から減少傾向にあります。他方で、大麻取締法違反については平成25年まで減少傾向にあったものの、以下のとおり、その後、急激に増加しています。あくまでも検挙された人員ですから、すでに大麻に手を出している少年を含めるとさらに数は増えるものと思われます。
平成25年 58人
平成26年 77人
平成27年 144人
平成28年 206人
平成29年 292人
大麻は薬物への入り口ともいわれており、その危険性について知らない、軽視している、あるいは誤った情報を得ているがゆえに気軽に大麻に手を出してしまっていることも原因の一つとなっているようです。
~薬物・少年事件と刑事手続~
警察の事情聴取では、シンナーの入手経緯、摂取状況、常習性等につき詳しく聴取されることとなります。その後、事件は検察庁、家庭裁判所へと送られることになります。調査の結果、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が認められず、更生に向けた環境が整っていると認められる場合などは「審判不開始」決定が出されることがあります。他方、大麻等の薬物に対する依存性・親和性が顕著で、少年の更生が必要と判断された場合は、少年審判が開かれた上で「少年院送致」「保護観察」などの保護処分が出されることになります。なお、犯罪を犯した少年に対しては保護処分を下されるのが通常で、上で述べた刑罰を課されるのは極めて例外となります。
~少年院送致を回避するには~
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者などを収容する施設で、少年に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。
少年院送致は少年審判で下される保護処分の一種ですが、少年の意思に関わりなく少年を施設に収容され、自由の利かない規律正しい生活を強いられる点で他の保護処分よりは厳しいといえます。
どんな場合に少年院送致になるかは一概にはいえませんが、特に、非行事実、非行歴などから犯罪傾向が進んでいる少年、更生・矯正に向けた環境が整っていない少年などは少年院送致となる傾向があります。他方、少年鑑別所の生活を通じて改善更生が見られたり、非行の原因となった家庭環境や生活状況、交友関係などの問題が解決しつつあると認められたりした場合には、少年が(少年院に収容されなくとも)社会の中で周囲の支えを得て立ち直ってゆくことに期待し、少年院に収容することまではせず、保護観察となることも少なくありません。
したがって、少年院送致を回避するには、少年審判が始まるまでに、少年の非行の原因を探り、更生に向けた環境を整備し、なぜ少年院ではなく社会内での矯正が妥当なのか、適当なのかを調査官や裁判官にしっかりアピールする必要があります。
そのためには、付添人である弁護士の力が必要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
中学生が器物損壊罪で取調べ
福島県双葉郡所在の中学校に通うAさん(15歳)は、「いじり」と称して自身が所属する野球部の後輩Vさんに様々な嫌がらせをしていました。
部活の大会が目前に迫ったある日、AさんはVさんを困らせようと考え、野球のユニフォーム一式を旧校舎にあるトイレの掃除用具入れに入れました。
VさんはAさんが犯人だと気づかず必死にユニフォームを探しましたが、結局見つかったのは大会の翌々日でした。
のちに周囲の発言などからAさんが犯人であることが明らかとなり、Aさん宅にVさんの母親から「双葉警察署に行きますから」という連絡がありました。
以上の経緯をAさんの両親から聞いた弁護士は、器物損壊罪が成立する可能性があることを指摘したうえで、保護処分について説明しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と器物損壊罪の区別】
あまりイメージが湧かないかもしれませんが、実は窃盗罪と器物損壊罪はよく似た点がある罪と言えます。
まず、器物損壊罪の条文は以下のとおりです。
刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 前三条に規定するもの(※)のほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※建造物、艦船および特定の文書
他人の物を「損壊」し、または「傷害」した者とあります。
後者は他人の動物傷つける場合を想定しており、今回注目するのは前者です。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切に行為を指すと考えられています。
つまり、文字どおり物を壊す行為のみならず、物を隠す行為についても「損壊」に含まれる余地があるのです。
ここで窃盗罪に目を向けると、窃盗罪はご存知のように他人の物を盗むというものです。
他人の物を持ち去った場合、それが盗む目的か隠す目的かは外見から分かるものではありません。
そのため、窃盗罪と器物損壊罪は必ずしも明瞭に区別できるとは限らないというわけです。
これらを区別する基準は、犯人の行動や発言から推測できる犯人の意図がどのようなものだったかによります。
簡単に言うと、物を使用したり売却したりして利益を得るつもりであれば窃盗罪に、そうではなく単に持ち主による物の使用を妨げるつもりであれば器物損壊罪に当たります。
上記事例のAさんは、ユニフォームの使用を妨げて嫌がらせをするつもりだった以上、器物損壊罪が成立すると考えられます。
【少年事件における保護処分の概要】
「少年」(少年法では20歳未満の者)が起こした刑事事件については、少年事件として成人とは異なる手続に付されるのが原則です。
少年事件と通常の刑事事件とでは様々な違いがありますが、大きな違いの一つとして最終的に下される処分の内容が挙げられます。
少年事件として取り扱われた場合、成人と違って刑罰を受けることはなく、代わりに保護処分という措置を受けることになるのが基本です。
保護処分にはいくつか種類がありますが、いずれも適切な教育を通した少年の更生が最も重視されている点で共通しています。
保護処分は審判(通常の刑事事件で言う裁判に相当)によって決まり、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
まず、少年院送致は、少年を本来の生活圏から離して少年院で生活させるというものです。
少年院では、学校と同じような教育を受けつつ規律ある生活を送り、少年に根ざした犯罪傾向の除去などに取り組みます。
次に、児童養護施設・児童自立支援施設送致は、児童の保護に主眼を置く施設で少年を生活させるというものです。
少年院送致や後述の保護観察に比べて保護の色彩が強く、たとえば虐待を行う親からの隔離が必要な場合などに選択されやすいと言えます。
最後に、保護観察は、少年を本来の生活圏に置きつつ定期的に経過を見守るというものです。
施設への収容が求められないため、比較的自由に過ごすことができるのが特徴と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、最適な保護処分を目指して少年ひとりひとりと真摯に向き合います。
お子さんが器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちらから)
中学生の業務妨害罪
福島県南会津郡に住む中学3年生のAさんは、夏休みに自宅で友人と遊んでいた際、じゃんけんで負けた人が罰ゲームをすることになりました。
その罰ゲームの内容は、近所にあるピザ屋に連絡し、適当な住所を言ってピザを5枚注文するというものでした。
じゃんけんの結果、Aさんが罰ゲームをすることになり、上記内容を実行しました。
その後、住所が存在しなかったことからピザ屋の店員が嘘だと気づき、南会津警察署に相談しました。
これにより、Aさんは偽計業務妨害罪の疑いで取調べを受けることになったため、Aさんの親が弁護士に今後の流れを聞きました。
(フィクションです)
【業務妨害罪について】
刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、…その業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、234条において、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」としています。
これらがいわゆる業務妨害罪の規定です。
業務妨害というと、店などの利益を低下させたことによる損害賠償を想定するかもしれませんが、上記のとおり刑事上の責任も問われる可能性があるのです。
先ほど引用した業務妨害罪の規定は、233条が偽計業務妨害罪、234条が威力業務妨害罪に関する規定です。
簡単に言えば、他人に対する嘘や他人による勘違いなどを利用するのが偽計業務妨害罪、暴行や怒号などを利用するのが威力業務妨害罪です。
条文には「業務を妨害した」とありますが、売上の低下や業務の停滞などの実害は必ずしも生じる必要がないと考えられています。
ですので、円滑な業務を妨げる危険性さえ認められれば、偽計や威力のみをもって業務妨害罪が成立する可能性があります。
上記事例では、Aさんがピザ屋に対し、適当な住所を言ってピザを注文しています。
このような行為は、本来ピザを注文するつもりがないのにそのように装うものであり、なおかつ本来不要な調理を求めるものです。
そうすると、「偽計」を用いて「業務を妨害した」として、Aさんの行為は偽計業務妨害罪に当たると言えるでしょう。
法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、後述のとおりAさんには刑罰が科されません。
【少年事件における処分】
罪を犯した者が20歳未満の者に当たる場合、少年事件として成年による通常の刑事事件とは異なる取り扱いがなされます。
以下では、上記事例のAさんについて、今後どのような流れで処分が下されるのか簡単に見ていきます。
まず、警察官と検察官が捜査を行う段階においては、基本的に通常の刑事事件と大きく異なりません。
取調べで捜査機関に呼び出されることもありますし、事案の内容によっては逮捕および勾留による身柄拘束がなされます。
ただし、長期の身柄拘束である勾留の請求については、「やむを得ない場合」でなければならないと少年法に定められています。
事件の捜査が終了すると、罪を犯したとされる少年は家庭裁判所に送致されることになります。
少年事件の場合、裁判で有罪となって刑罰を科されたり、逆に裁判が開かれず不起訴で事件が終了したりすることはありません。
これは種々の政策を通して少年の健全な育成を達成するという趣旨に則っており、少年事件最大の特徴と言えます。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、面談などを通して少年の資質、性格、能力などを把握し、必要に応じて少年審判という裁判に代わる手続を行います。
少年審判が開かれた場合、①不処分、②保護観察、③児童自立支援施設または児童養護施設送致、④少年院送致のいずれかが選択されます。
②から④をまとめて保護処分と呼び、事件の内容や、その時点における少年の更生の可能性などを主に考慮して決定されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、少年事件に関する疑問に丁寧にお答えします。
お子さんが業務妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
高校生が通貨偽造罪で逮捕
福島県田村郡に住むAさん(16歳)は、両親がお金に厳しく、月に1000円程度しか小遣いがありませんでした。
そのため、友人からの遊びの誘いをいつも断っており、そのたびにお金が満足に使えないことを疎ましく思っていました。
そこで、自宅のプリンターを用いて1万円札をカラーで印刷し、それを財布に入れていました。
ある日、Aさんがその偽札を使ってコンビニで買い物をしたところ、その翌日に店員が偽札であることに気づいて警察に通報しました。
これにより、家宅捜索が行われたうえで、Aさんは通貨偽造罪の疑いで田村警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、少年院に行くことになるのか弁護士に尋ねました。
(フィクションです)
【通貨偽造罪について】
通貨偽造罪は、「行使の目的」で通貨(日本で使用できる硬貨や紙幣)を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
簡単に言えば偽物のお金をつくった際に成立する罪ですが、少し複雑な罪なので詳しく解説していきます。
まず、「行使の目的」とは、偽造したものを真正な通貨として流通させる目的を指します。
このことから、たとえば学校の授業の教材として利用するために偽札をつくった場合には、通貨偽造罪は成立しないと考えられます。
次に、「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た見た目のものを作成することを指します。
ただし、既にある通貨に加工を加えた場合は「偽造」ではなく「変造」となり、通貨偽造罪ではなく通貨変造罪に当たります。
とはいえ、罪名こそ違えど法定刑は同じなので、この違いが処分の結果に大きく影響するケースは多くないでしょう。
上記事例のAさんは、買い物などに使用する目的で、1万円札をカラープリントしています。
そうすると、「行使の目的」で「通貨」を「偽造」したと言えることから、Aさんには通貨偽造罪が成立すると考えられます。
更に、これをコンビニで使用していることから、偽造通貨行使罪も併せて成立することが見込まれるでしょう。
ちなみに、仮にAさんによる偽造が雑で、偽札の出来が一般人を誤信させるに至らないものだった場合、通貨偽造罪は成立しない余地が出てきます。
ただ、その場合には、通貨及証券模造取締法という法律により別途罰せられる可能性があるため注意が必要です。
【少年院送致とは】
上記事例のAさんは少年(20歳未満の者)であることから、通常の刑事事件ではなく少年事件として手続が進む可能性が高いです。
少年事件の特色というのはいくつか挙げられますが、中でも最も重要なのは最終的な処分です。
少年事件の場合、少年に適切な措置を施して正しい道へ導くという趣旨から、刑罰ではなく保護処分というものが行われることになっています。
この保護処分には、①少年院送致、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③保護観察、の3つがあります。
また、こうした保護処分以外に、そもそも保護処分を決めるための審判すら開かない審判不開始、審判の結果何らの保護処分にも付しない不処分というものもあります。
上記保護処分のうち、一般的に知名度が高く、なおかつ避けたいという声が多いのはやはり少年院送致ではないかと思います。
少年院送致とは、少年を少年院に収容し、そこでの生活を通して健全な育成を目指すというものです。
一般的に、非行に及ぶ傾向が強いなど要保護性が大きい少年に対して行われます。
こうした点から、少年院送致を避けるためには、少年院に行かずとも少年の更生が目指せると言えるような環境を整えることが重要です。
そうした環境整備のことを含め、少しでも不安があればぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の経験豊富な弁護士が、少年院に行かせたくないというご要望に沿えるよう全力を尽くします。
お子さんが通貨偽造罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
Newer Entries »